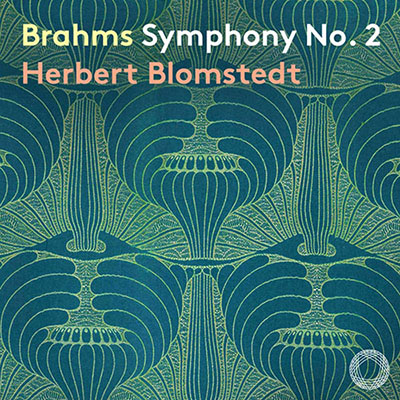今回は2021年に個人的に良いと思ったクラシックの新作アルバムを紹介します。
クラシック音楽は例年にも増して盛況で、大手からマイナーレーベルまで優れた作品が多い一年でした。とりわけイヤホン・ヘッドホンの性能が引き出せるような高音質盤を各ジャンルごとに選んでみたいと思います。
2021年
2021年は自宅でじっくりと音楽を聴く時間が増えたことで、新作アルバムを聴いた数は例年よりも多かったように思います。
サブスクリプションストリーミングの時代になっても、私自身はあいかわらず海外のレーベルサイトとかを巡回してFLACやDSFファイルでダウンロード購入する事が多いです。タワーレコード オリジナル企画SACDなど、ダウンロード盤が出ていないものは物理ディスクを購入しています。
クラシック専門のダウンロードショップはやはり英国のPresto Musicが強く、新譜情報や独占インタビューなどサイト内容が充実しています。もちろん他のダウンロードショップも巡回して最安を探したりはしますが、まだ44.1kHz/16bitで出しているレーベルもあったりして、そういうのはハイレゾショップでは見つからず、PrestoやQobuzなどに頼る事になります。
ストリーミングでも近頃はロスレスが一般的になってきたおかげでダウンロード購入するメリットは薄れましたが、どのサブスクサービスもカタログの穴が多いのと、メタデータ管理と検索が絶望的に悪く、とくにクラシックは同じ演目が複数あるため、どの録音なのか、どのリマスターなのか(UPN/EAN番号)が不明瞭で、まだ使い物になりません。
2021年はApple Musicの低価格ロスレス到来で、これまでロスレス高音質を謳っていたプレミアムストリーミングサービスはことごとくピンチに陥っているようです。たとえばソニーのMora Qualitasが早々に白旗を掲げてサービス終了を発表したのが象徴的です。
音楽以外のサブスクも、最近のニュースを見ると、ずっと無料だった企業向けG Suite・Google Workspace (ドメイン登録してのGmailやカレンダーなど)が2022年から有料になると発表があったり、スポーツライブ配信のDAZNがいきなり大幅値上げするなど、定額クラウドサービスに依存するリスクも露見しはじめています。
過去にAmazonやUber Eatsでも見たように、シェア争いが起こっている最中は投資家が身銭を切って赤字覚悟の価格競争になるので、我々消費者が恩恵を受けて「今までCDやダウンロードを買っていたより断然安い」と喜びますが、一旦ライバルを駆逐すると収益化が求められて一気に値上がりするという図式です。企業が横暴なのではなくて、今の安さが持続不可能な出血大サービスなのです。
そして値上げを行うと「やっぱり高いから解約しよう」というカジュアルユーザーが増えて、レーベルやアーティストへ還元される金額のプールが減って、離脱するレーベルが出てきたりでサービスが低下して、という悪循環のスパイラルに陥りがちですから、そのあたりが今後どうなるのか気になります。
クラシック関連でのニュースといえば、これまでクラシック専門のサブスクリプションサービスとして奮闘していたPrimephonicが2021年8月にAppleに買収されて、サービス終了が発表されました。2022年中にAppleから新たなサービスプラットフォームが登場するらしいです。
Appleにとってはサービスの穴を埋めるだけの安い買い物だったのでしょうけれど、クラシックファンからすると、まともなサービスになるか一抹の不安があります。熱心なクラシックマニアの要望に耐えうるような細やかなサービスを提供する覚悟があるのか、それともいわゆる若手イケメン美人クロスオーバーのポピュラークラシック風アレンジ名曲コレクションを押し付けるスタイルになるのか、アップルなら多分後者になるだろうという心配があります。
私みたいにダウンロード中心の人にとっても、ストリーミング中心の社会になったことで憤りが積もる一年でした。2020年の繰り返しになりますが、交響曲などから一楽章や一曲だけを引き出した「先行シングル」リリースが急増しており、いざアルバムが発売してもカタログの奥深くへと埋もれてしまいます。
これはサブスク上で利益を出すために「一曲」に対する再生完了回数が重要なので、一時間の交響曲をそのままリリースしても利益が出せないため、ひとまず短い一曲だけをトップチャートに乗せて何度も再生させるという苦肉の策をとっているからです。クラシックを真面目に聴く人は一楽章だけみたいな聴き方はしないわけですから、再生回数によるビジネスモデル自体が実情と合っていないというのが問題です。
私みたいなクラシックマニアに対しても、出所不明のキャッチーな一楽章だけ集めたリラックス名曲集とか、薄っぺらいクリスマスコンピやベストヒットアニメアレンジみたいなカジュアル路線ばかりをアルゴリズムが勧めてきて、本来聴くべきアーティスト新譜がリスナーの目に届かないのは、ランキング形式による大衆向けシステムの根本的な問題でしょう。つまり自力で好きな音楽を開拓する気力を削いで、オススメ上位に載る作品だけで世界中の音楽が手中にあるような錯覚を抱かせるシステムです。
ポップスでも、ストリーミングのトップページに現れる「推奨プレイリスト」誘導形式のせいで、アーティストの実像が失われて、ただ消費するだけの一過性のシングル曲の寄せ集めという傾向が強まったようで、それがクラシックにも起こりつつあるという事です。
プロ音楽雑誌でも近頃は「ストリーミング時代の音楽プロデュース必勝法」みたいな記事が多く書かれており、再生回数を稼ぐために肝心なのは、とにかく最後までスキップされずに「聴き流せる」曲であることが重要視されるため、楽曲途中の展開などはNGで、単調であることが求められているようで(実際に2021年ヒットチャートを見てもそのようです)、作曲手法も「イントロは無し、ブリッジも無し、第二主題や転調も無し」というのが当然になってきており、大げさに言うなら、大衆音楽における300年続いたAABAソナタ形式の覇権がついに瓦解する、歴史的なターニングポイントを目の当たりにしているのかもしれません。
また、つい最近のアメリカの記事では、ここ数年でポップスを含めて新しいアーティストの影響が弱まり、古い音楽を聴く人の割合がどんどん増えており、2021年は米国音楽市場のおよそ70%が古い音楽によるもので、逆に新人アーティストを積極的に起用しようとするプラットフォームが減っているという事で物議を醸しています。古典的なレコードレーベルやラジオなどはまさにそうですが、ストリーミングサービスのアルゴリズムも再生回数を基準にオススメを提示するという「負のループ」が積り重なることも問題視されています。
新しいアーティストが活躍できるプラットフォームとしてソーシャルメディアがあるではないかという主張もありますが、フラグメント化されており、昔のように特定の新しいジャンルが増強しあって、それまで興味が無かった一般大衆にまでブームになるという事が起こりにくいのが問題のようです。
前置きが長くなってしまいましたが、ようするにクラシックを聴くといっても、大手サブスクプラットフォームが想像しているような売り方と、真面目なレーベルやアーティストが求めている売り方に大きな隔たりがあるというだけであって、クラシックの作品リリース自体は2021年も非常に充実しているので、それらをどうやって多くの人に届けて、興味を持ってもらえるのか、というのが目下の課題だと思います。
なんにせよ、皮肉めいていますが、今回紹介するアルバムの多くは大手サブスクリプションサービスでも聴けると思うので、興味が湧いたらぜひ自力で検索して聴いてみてください。
2021年の優秀アルバム
オーケストラやピアノなどのメジャーなジャンルに行く前に、ひとつだけ、それらに該当しない、2021年で極めて素晴らしかったアルバムを一枚紹介します。特にオーディオマニアは必聴です。
Chandosの「More Honourable than the Cherubim」です。重厚なロシアの男性コーラスという、私も普段あまり好んで聴かないジャンルなのですが、このアルバムは凄いです。女性セクションがいないと帯域が狭くて単調だろう、とか、どの曲も一緒だろう、なんて疑っていたものの、いざ聴いてみると驚異的な音響体験が繰り広げられます。
PaTRAM Instituteというアメリカにあるロシア正教音楽研究団体がロシアの辺鄙な教会で録音した作品です。日本人は合唱に興味が無い人が多いと思いますが、このアルバムを聴けば、なぜ合唱が音楽史上最高の楽器と言われているのか納得できるかもしれません。
優れた合唱団は各自がその場の音響による音波干渉の微細なゆらぎをリアルタイムで感じ取って、超微分音で修正することで、たとえ同じ和声であっても、歌詞の伝えたいメッセージに応じて質感を臨機応変に変化することができます。つまり鍵盤で決められた和音を押すだけでは絶対に実現できない、まるで人間の声とは思えない複雑なマイクロトーナルなせめぎあいが体感できます。
スピーカーやヘッドホンの性能を評価するのにも最適なアルバムです。全帯域が非常に厚く、しかも繊細に録音されているため、ドライバーの性能が不十分だったり、ハウジング反響が管理できていないヘッドホンで聴くと、特定の周波数帯域だけシュワシュワと濁ったようなノイズが乗るのにすぐに気が付きます。オーディオ機器の不具合や問題点を洗い出すテストディスクとして2021年はかなり重宝したアルバムでした。
オーケストラ作品
交響曲などの管弦楽作品では、とりわけ二枚が印象に残りました。まず一枚目は、BISからSusanna Mälkki指揮ヘルシンキのバルトーク「管弦楽の」と「弦チェレ」というメジャーな組み合わせです。べつに最高の名演というわけでも、自分にとってのベスト盤でもないのですが、とにかく独特で印象的な一枚でした。
Mälkkiの指揮はブーレーズをドーピングしたかのような非常にカッチリと明確な演奏で、オケの技術とBISの透明感のある録音スタイルも相まって、DAWに打ち込んだEDMかのようにゆらぎのない作品に仕上がっています。しかも、ただ単調にリズムを刻んでいるのではなく、オケの表現力はかなりエッジが効いていてスリリングなので、まるでハイリスクな曲芸を見ているかのように、一気に聴けてしまいました。
印象に残った二枚目はAccentusからJakub Hrůšaとバンベルク交響楽団のブルックナー4番です。このアルバムは総計4時間半で第4番の3つの版を全部収録しているというのが話題になったわけですが、演奏自体がとても良いため、この風変わりな企画のために敬遠した人もいるかと思うと、どれかひとつの版に絞って値段を安くしてくれたほうが良かったかもしれません。
ここ数年でフルシャは各国から引っ張りだこの大スターになっているのも、今作を含む彼の最近のアルバムを聴いてみれば納得できます。優しく情緒あふれる親密な演奏はこれまでにない新鮮さがあり、フルシャだから聴いてみようという気にさせてくれます。
先程のMälkkiのバルトークと同様に、このブルックナー4番は個人的なベストというわけではなく、王道が聴きたければベームとかの定番は色々あるわけですが、今作はとにかく解像感が圧倒的に高いです。レコーディングの音質が良いだけでなく、フルシャとバンベルクの解釈による部分が大きいと思いますが、まるで作品をX線で透視しているか、一つ一つの構成部品に解体したかのような、とても不思議な感覚です。スケール感が大きく堂々とした一般的なブルックナーの解釈とは違い、譜面の詳細まで掴み取れるような解像感があり、しかもバラバラにならず統率がとれています。版の違いを体感するにも最適なアルバムだと思います。
ブルックナーつながりで、ProfilからChristian Thielemann指揮SKDのブルックナー1番も、上のフルシャとは真逆の観点でとても楽しめました。定番の1877年リンツ稿版です。
ティーレマンは同時進行でソニーとウィーンフィルとのブルックナーシリーズも出ていますが、私としてはこちらProfilのSKDとのやつを聴いてもらいたいです。今後ソニーとも1番が出たら聴き比べてみるのも面白いでしょう。
近頃はブルックナーのリリースが多いので色々と聴いていて「まあどれも優秀でしっかりした演奏だな」なんて思っていたわけですが、いざティーレマンの一番を聴いたら、もう再生開始の数秒から他とは全然レベルが違うので、今までなんて無駄な時間を費やしたんだと愕然としました。ティーレマンは客演だと慎重でかっちりした演奏が多いのですが、SKDとの作品はどれも派手に飛ばしていて爽快です。オケの音色がとにかく濃く、楽器の響きを聴いているだけでも満足できます。優れたオケというのは、緻密な解釈とか正確さとか以前に、やはり音色そのものが魅力的であるのが大前提だということを教えてくれます。
BR KlassikからKent NaganoとBRのメシアン管弦楽集も優秀でした。メシアンは他の作曲家のアルバムの穴埋めに小曲をチラホラ見かける程度が多いので、ここまでガッツリと大曲尽くしのアルバムというのは久しぶりです。「ミのための歌」「クロノクロミー」と後期の傑作続きから「キリストの変容」という、メシアンファンにとっては大変嬉しい選曲に、メシアン直伝のベテランであるナガノの指揮で、BRの真面目で迫力のある演奏ですから、十二分に楽しめました。
Antonio Pappanoはオーディオマニア向けのアルバムが多かったです。LSO Liveからはヴォーン・ウィリアムズ4&6番とタリス幻想曲がどちらもDSD256ネイティブ録音で、コンセルトヘボウRCO LiveからはベルリオーズのレクイエムがDXDネイティブでリリースされました。
どちらもパッパーノなので雄大な演奏なのは当然のこと、DSD256・DXDフォーマットの極限まで引き出すような優秀録音なので、これらのフォーマット対応のDACをお持ちなら、テストディスクとしても活用できます。スペックで対応しているだけで電源とかの性能が伴っていない安易なオーディオ機器だと、タリス幻想曲の宇宙的なスケール感は描ききれません。
パッパーノは他にもワーナーでサンタ・チェチーリアとのシュトラウス英雄の生涯や、Janine Jansenが12本の異なるストラディバリを弾き比べる12 Stradivariではピアノ伴奏役をするなど、本当に多方面で活躍しています。
OndineからRobert Trevino指揮バスク国立管弦楽団のラヴェルも良かったです。フランスのオケでないと本物のラヴェルは演奏できない、なんてよく言われますが、それを言うならバスクでないとラヴェルは理解できない、というべきでしょう。Ondine特有の録音手法もあって、ただ単にスタイリッシュでエレガントなだけでない、キラキラと輝き奥深いラヴェルが味わえます。スペイン狂詩曲やラヴァルスなど、昔の推奨盤を聴いたきりという人は、あらためて新鮮な発見があると思います。
Trevinoはアメリカ出身ということもあり、同じくOndineとバスク管でAmericascapesというアルバムも出しており、そちらも風変わりな選曲で充実した作品です。
François-Xavier Rothも相変わらず精力的に多方面で色々出しており、2021年はケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団とのシュトラウス「ドン・キホーテ」「ティル」のアルバムが印象的でした。
ロトとケルンというと、以前のマーラーは個人的にあまり好きになれず、最近のLes Sièclesとのアルバムもそこまでグッと来るほどでもなかったので消極的だったのですが、このシュトラウスは良いです。何を隠そうドン・キホーテとティルのどちらもこのケルンオケで初演されたという、シュトラウスと縁の深いオケですので、伝統と意地もあるのでしょう。
鋭い立ち上がりでキビキビと演奏してくれて、長いドン・キホーテもダレずに楽しめました。チェロはHarmonia MundiということでQueyrasなのでシュトラウスとの相性は心配でしたが、意外と好印象でした。ロトのテキパキしたオケと上手くマッチしているのでしょう。ティルも早回しのようにスピーディーですが聴いていれば慣れてきて快適です。
ロトは10年前にもHänsslerでSWRともシュトラウス管弦楽集を5枚組で出しているので、その頃と比較してみるのも面白いです。(そちらも全集としてかなりクオリティが高いです)。
クリーヴランド管弦楽団の自主レーベルから、Franz Welser-Möstのプロコフィエフ2番も凄かったです。その昔クリーヴランドは世界最高の技術を誇るオケと呼ばれていた時代があったわけですが、あれから何世代も経った今でも、ウェルザーメストの指揮でその片鱗が伺えます。
作風が意味不明で敬遠されがちなプロコフィエフ2番も、クリーヴランドの刀のように研ぎ澄まされた演奏のおかげでプロコフィエフ独自の舞踏のようなリズムが浮き彫りになり、作曲の真価が伝わってきます。録音もロシア風のギラギラした咆哮とは一味違い、木管などの綺麗な音色がクリアに再現されて、極めて優秀です。
Reference RecordingsのManfred Honeck指揮ピッツバーグ交響楽団から2021年はブラームス4番でした。このレーベルのシリーズは個人的にどうしても好きになれないけれど技術的には物凄いのでつい買ってしまう、というのが毎年恒例になってきており、今作も例にもれず同じ感想でした。
相変わらず、まるでハリウッド映画サントラのように物凄い高解像でダイナミックな演奏で、録音の細部までツヤツヤに磨かれ、とくに第三楽章の出だしなど人間業とは思えないくらいキッチリと進行していきます。しかし、ソロパートになったら同じ楽器が全然違う音場定位から現れたり、帯域ごとに響くステレオ位置が違ったりなど、まるで全ての楽器をマルチトラックで個別に調整しているかのように不自然なブツ切り感があります。後年のカラヤン録音とかに近い芸術性を求めているのでしょうか。
実際にピッツバーグでライブ公演を聴いてもこんな体験はできないので、そういった意味ではちょっと好みに合いませんでした。アメリカの巨大なハイエンドオーディオシステムを思い切り鳴らすのに最適だと思うので、そういうオーディオデモ用ディスクを探している人には絶対にお勧めできます。
ブラームスなら、こちらPentatoneのHerbert Blomstedt指揮ゲヴァントハウスの方が断然好みに合います。2020年に1番が出て、その堂々たる演奏に感動したところ、2021年は2番が出ました。
ブロムシュテットの明確で知的な解釈はPentatoneの分厚い濃厚なサウンドとの相性も良く、ここまで王道で満ち足りた演奏は近頃そうそう無いだろうと思います。上のホ-ネックとは対象的に、こちらのブロムシュテットは一見響きが厚くて不明瞭なようにも感じますが、優れたオーディオ機器でじっくり聴いてみると、管楽器も打楽器も、ちゃんと前方遠くの正しい距離感で存在していて、しっかり聴き分けられます。まるで油絵のように厚いグラデーションの中に忠実な奥行きの立体感が描けているといった感じでしょうか。つまり個々のパートをミキサーで前に出して強制的に「聴かせる」のではなく、作曲家本来が意図した管弦楽法の和声バランスを保ち、厚いシンフォニーを堪能しながら、その細部にまで興味がある人は注意して覗き込めばしっかりと解像してくれる、というのが理想的な録音だと思います。
それにしてもブロムシュテットは凄い指揮者ですね。思い返してみると、ベートーヴェン全集はエテルナでSKDと、Accentusでゲヴァントハウス、ブルックナー全集はMDRでゲヴァントハウスと、どれも全集のナンバーワンに選んでもおかしくないくらい優秀な名盤を残しています。このPentatoneとのブラームスもぜひ全集として完成を目指してもらいたいです。
Avi MusicのAdam Fischer指揮Düsseldorfer Symphonikerのマーラー全集も2021年には2番と6番が出てついに完成を迎えました。2016年に7番から始まって、長い道のりでした。
奇しくも弟Ivan Fischerのブダペストでの全集が8番を残して宙吊りになっている状態なので(8番は駄作で嫌いだそうです)、遅れて始まったAdamの方が先に完成してしまいました。
このデュッセルドルフとの演奏は、マーラーでよくありがちな、パッセージごとに自己流の解釈を加えるようなタイプではなく、あまりテンポを崩さず颯爽と流れるような演奏なので、逆にちょっとした表情の変化に「おやっ?」と興味を惹かせてくれます。
とりわけ2番と6番というと迫力満点な演奏を想像していると、私も今作を初めて聴いたときは気が抜けているようで拍子抜けしたのですが、それから何度もくり返し聴くことで、だんだんと意図している事が伝わってくるように思います。煮えたぎるような情熱的なマーラーを期待している人には不評かもしれませんが、演奏の解釈が誠実で細やかなところまで行き届いており、全集としての統一感もあるので、将来的に高く評価される名演だと思います。
協奏曲
協奏曲のアルバムでは、ノルウェーLAWOレーベルからSonoko Miriam Weldeとオスロフィルのブルッフ・バーバーが凄い高音質盤でした。
ケレン味あふれるメロディがベタすぎて最近は敬遠されがちなブルッフ・バーバーの二本立て(しかも間奏に揚雲雀)ですが、やはり今作のように若手新人がスカッと演じきるのはカッコいいです。
LAWOらしい広大で見通しの良い録音で、しかもDXDネイティブで、オスロフィルですから暑苦しくならず、Weldeのヴァイオリンも熱演タイプというよりは開放的に音を広げるようなスタイルなので、全体的に様々な要素がいい感じに組み合わさって素晴らしいアルバムに仕上がっています。
LSO Liveは先程のパッパーノのヴォーン・ウィリアムズも凄かったですが、こちらのモーツァルト協奏曲集も素晴らしい高音質盤でした。
Jaime Martinの指揮で、ホルン、オーボエ、クラリネット協奏曲のどれもLSOの主席がソロを任されており、続いて協奏交響曲K297bと、最後にグランパルティータという豪華なラインナップです。スターソリストを起用するよりも、こういう内輪で行う方が親しみもありリハーサルも上手くいくので良い結果になると思います。実際に演奏は新鮮で一体感がある素晴らしい仕上がりです。
録音の方もBarbicanではなくてLSO本拠地のJerwood HallでDSD128/256ネイティブ録音だそうで、それらを再生できるDACがあるなら、ぜひ最高音質で堪能する価値がある作品だと思います。
旧エテルナの復刻しかやっていないような印象のBerlin Classicsも新譜をいくつか出しており、その中でもEmmanuel Tjeknavorianのブラームスヴァイオリン協奏曲は良かったです。Cristian Măcelaru指揮WDRというわけでとりわけ目に留まるリリースでもなかったのですが、久々のブラームス協奏曲ということで興味本位で聴いてみたところ、ずいぶん気に入りました。
チェクナヴォリアンというと、昔ASVでそういう指揮者がいたなと思ったら父親だったので、時代の流れを感じます。そんな息子のヴァイオリンは、鋭角で朗々とした、まるで私が愛してやまないコーガンの片鱗を感じさせるような、自信を持って音をリスナーに届けてくるような演奏です。
ブラームスといえば、2021年はなぜかピアノ協奏曲1番のリリースが多かったので、順番に聴き比べてみると面白いと思います。演奏家によって目指す方向性がここまで違うのかと、クラシック音楽の奥深さを再認識できます。
ECMのSchiffとHMのMelnikovはどちらも初演当時のピリオド楽器ということで1859年式ブリュートナーを、LDVのCouteauはスタインウェイD274、SignumのDespaxはファツィオリ278ということで、奏者はもちろんのこと、楽器の聴き比べも楽しめます。
ブリュートナーは流石に現代の耳で聴くとおもちゃみたいでパワーや色艶が弱く感じますが、そもそもブラームスの一番は重厚すぎるので、この楽器で聴くことで新鮮な見方ができます。個人的にはDespaxのがAndrew Litton指揮BBCということもあって普段我々が期待するブラームス一番として理想的な演奏だと思いました。
AlphaからOlga Pashchenkoのモーツァルトピアノ協奏曲9 & 17も奇抜で面白いアルバムでした。フォルテピアノで、9番には1788年のシュタイン、17番には1792年のヴァルターのレプリカを使っているということで、確かにそれぞれ音色が違い、演奏の雰囲気も大きく変わります。
オケはIl Gardellinoというベルギーの古楽器グループで、超小編成なので、普段聴き慣れているものと比べるとアンサンブルのバランスがまるでピアノと交互にソロやデュエットを回しているような奇想天外な感覚です。おかげでずいぶん集中力が必要ですが、演奏に没頭する充実感も非常に高いです。
理由はわかりませんが、2021年はカステルヌオーヴォ=テデスコのギター作品集をよく見かけました。まだ著作権が切れたわけでも無さそうですし、急にリリースが増えたのは不思議です。クラシックにおけるギターの作品自体が少ないので(音量が小さすぎてコンサートに向かないというのが最大の理由ですが)、そんな中でカステルヌオーヴォ=テデスコはクラシックギターを志す人にとっては感謝してもしきれない存在です。(もうひとりはヴィラロボスでしょうか)。
StradivariusレーベルのDuilio Meucci、NaxosのLeonard Becker、DeccaのGiampaolo Bandiniなど、どれもギター協奏曲を中心に収録曲はだいたい同じで、録音品質も優秀なので、交互に聴き比べてみるのも面白いかと思います。
室内楽
オーディオファイル的に2021年で一番楽しめた室内楽アルバムはEudoraレーベルからFernando Arias & Noelia Rodiles 「Slavic Soul」でした。
ドホナーニ、ヤナーチェク、ショスタコーヴィチによるチェロとピアノのデュオという、普段ならワイルドに演奏されがちな演目も、このアルバムではレガートの余韻と息使いを十分に使って、落ち着いた哀愁のある綺麗な演奏に仕上がっています。いつもどおりスペイン・サラゴサのホールでのDSD256ネイティブ録音で、ブックレットによるとSonodore RCM-402とPearl CC 22マイクを使っているとのことですが、チェロとピアノのどちらも力強さと美音が両立できている、ハイレゾ生録のお手本のようなアルバムです。とくにドホナーニの変奏曲なんて音色が素晴らしすぎて耳が離せません。
Eudoraレーベルは2021年は他にもお隣カタロニアのモンポウ「ひそやかな音楽」やブラームス・シューマンのクラリネット作品など、優れたアルバムをリリースしてくれました。
もう一枚、音質と演奏の凄さに圧倒されたのは、BISからWigmore Soloistsのシューベルト八重奏曲です。
名前の通り、ロンドンのクラシックの殿堂ウィグモアホールを本拠地に、有名なクラリネット奏者Michael Collinsが立ち上げたグループということで、お披露目にはやはりシューベルト八重奏が定石でしょう。これまでに多くのレーベルがスターアーティストを集めて八重奏を出してきていますが、個人的には今作がベストです。奇しくもヴァイオリンのIsabelle van KeulenはDGGクレーメルの1988年盤でも出ていたので、彼女の成長と解釈の変化を聴き比べるのも面白いです。
各メンバーの演奏技術はもちろんのこと、音質面でも最高レベルに到達しており、ヴァイオリンが美しすぎる、と思ったらクラリネットが、ホルンが、と立て続けに凄い美音が押し寄せてくるので、今作を担当した制作チームの音作りのセンスと技術力に脱帽します。Wigmore Hallということで、これまでWigmore Hall RecordingsやResonus、Hyperionなどに関わってきたDavid RowellのFiLO Classicalがエンジニアを担当しているため、普段のBIS(Take5 Music Production)とは一味違ったサウンドです。
BISつながりで、Frank Peter Zimmermann & Martin Helmchenベートーヴェン・ヴァイオリンソナタ集も、まさに演奏家の美しい音色が存分に堪能できる作品です。2020年の第一巻に続いて2021年は残りの2枚が登場、近代的な全集としても価値のあるシリーズになりました。
Zimmermannのストラドの豊かな色彩に対して、Helmchenは最近話題のクリス・マーネの平行弦ピアノを使っており、コンサートに耐えうる大音量を重視した一般的なグランドピアノと比べて、より親密で洗練されたクリスタルのような音色が楽しめます。二人の息のあった誠実な演奏のおかげで、新しいようでいて昔懐かしいような、とても良い雰囲気の仕上がりです。
Fuga LiberaレーベルのSylvia Huang & Eliane Reyes 「Lointain passé」も演奏と録音の美しさに感激しました。
ルクーのヴァイオリンソナタからイザイの小品という選曲を見ると、新人コンクールの腕自慢みたいな勢いだけのアルバムを想像するかもしれませんが、今作は指先の技術を超えて、演目をしっかり自分のものにした演奏だと感じました。(そもそも小手先の若手新人だったらFuga Liberaで出さないでしょう)。ヴァイオリンとピアノのどちらもリラックスした柔らかな音色で、音楽の展開がどこに向かっているのかを予感させてくれるような自然な流れがあります。
こういうのを聴くと、古い推奨盤ばかりにとらわれず、新しいアルバムを聴いてみるべきと主張したくなります。
室内楽のシリーズでとくに充実していると思ったのは、Naxosの「History of the Russian Piano Trio」です。
演奏家の名前がThe Brahms Trioなので困惑しますが、ロシアロマン派のピアノトリオ作品集です。2020年11月に第1巻が出てから、2021年は第5巻まで続々とリリースされました。どれもジャケットが似ているので、「あれ?こないだ買ったっけ?」と迷ってしまうのが困ります。
トリオのメンバーはモスクワ音楽院を拠点に20年以上も研究と演奏活動を行っており、ジャケット写真でもわかるように音楽院の大ホールでの録音ですので、タイトルどおりロシアピアノトリオの歴史を語るに相応しい、由緒正しき錚々たる演奏です。
チャイコフスキーやリムスキー・コルサコフなど有名なところから、アレンスキー、タネーエフなど玄人好みな作曲家に移り、最新の第5巻ではユフェロフやスターンバーグなど名前すら聴いたことがないマニアックな領域に入っていきます。これで終わりなのか、ソヴィエト作曲家に突入するのかは不明ですが、現状でも十分に充実したシリーズです。
偏見かもしれませんが、ロシアのアーティストがモスクワ音楽院でロシアのスタッフによって録音されているということで、その鮮烈なサウンドはまるでソ連時代のメロディヤを連想させてくれました。もちろん音質自体は圧倒的に進化しているのですが、たとえばアレンスキーのフィナーレの竜巻のような激しさは、やっぱりこれぞロシアだな、なんて気分を奮い立たせてくれます。
EratoからQuatuor Ébèneの「'Round Midnight」も面白い企画盤でした。毎回なにか派手な事をやってくれるエベーヌ四重奏団らしく、今作ではミッドナイトをテーマとして、デュティユーの四重奏「夜はかくの如し」から始まり、Raphaël Merlinという新鋭作曲家の「Night Bridge」という作品から、シェーンベルクの「浄夜」という流れで、まさにジャケット絵のような星空を仰ぐ情景を彷彿とさせてくれます。
MerlinのNight BridgeというのはMoon RiverやStella by Starlightなどスタンダード曲のテーマを使ったアレンジなので、とても親しみやすく、しかもトリッキーで面白い作品です。シェーンベルクの浄夜はクラシック史上でもっとも美しい曲の一つだと思うので、ラストは爽快に満たされた感じで終わってくれます。
ところで、私を含めてデュティユーは難解で敬遠している人も多いと思いますが、その次のMerlinの歌謡曲風作品を聴いた後だと、それらのメロディ主旋律が無くなって伴奏のみになった部分とデュティユーはなんとなく同じような聴き方ができるな、なんて思えて親しみが持てるようになりました。そういった意味でも繰り返し聴く価値がある、上手く構成されたアルバムだと思います。
ピアノ
ピアノソロで印象に残った作品は、まずソニーからIgor Levitのショスタコーヴィチ24のプレリュードとフーガが挙げられます。
レヴィットは社会派っぽくて大衆メディアの推しも強く、ニューエイジな時代の寵児といったイメージがあるので、絶賛するのもなんとなく気が引けるのですが、演奏自体は本物で、確かに凄いピアニストだと思います。似たような感じにDGGが最近推しているトリフォノフとかも演奏は至極真っ当なので、スターだからとあえて敬遠するのももったいないです。
ショスタコーヴィチの24P&Fは大作がゆえになかなか録音されることがなく、数年に一枚出るか出ないかといった感じなので、新譜が出るのは単純に嬉しいです。数年前のベートーヴェンと同様に、レヴィットは基本を抑えながらスタイリッシュというか、親しみやすく工夫するのが得意で、いわゆるロマン派ピアニストが髪を振り乱しながら鍵盤をガシガシ叩くようなイメージとは正反対です。特にこのショスタコーヴィチはメカニカルに弾いてもドラマチック過ぎても上手くいかず、ある種の直感というか、遊び心が求められるため、レヴィットのスタイルに合っているようで、ずいぶん楽しめました。
個人的には最近のメルニコフとか定番のニコラーエワよりも、デッカのアシュケナージのが一番好きなのですが、このレヴィットのもそれに迫るくらい気に入っています。
レヴィットと比べると地味なリリースになりますが、ChandosからImogen Cooperの「...le temps perdu...」も楽しめました。2021年には大英帝国司令官騎士勲章を授与されるなど、もはや超ベテランになったCooperは凄いピアニストだと思うのですが、日本ではどうにも知名度が低いのが残念です。国内であまり流通していないChandosと長年やってきたせいでしょうか。
今作はCooperが幼少期に演奏したきり疎遠になった演目を振り返ってみるということで、タイトルの「失われた時間」というのもセンスが良いです。ラヴェルの「高雅で感傷的な」と「ソナチネ」で始まり、リストを交えて、フォーレの変奏曲Op.73という理想的な選曲です。若くしてパリのコンセルヴァトワールから始まり、二十歳でブレンデルに師事するためウィーンに移り、以降イギリスを拠点に活躍するという彼女の人生から、今作の収録曲も、14歳の当時にタイムスリップするような感覚と、そこから積んできた経験を元に生まれる新たな解釈とのせめぎあいみたいなものがあるのでしょう。どれも奥深く考えさせられるような演奏です。
ラヴェルつながりで、Evidence ClassicsからClément Lefebvreのラヴェル集も素晴らしかったです。哀愁を誘うCooperとは対象的に、こちらは明るく生命力が発散するような演奏で、演奏技術はもちろんのこと、オーソドックスな解釈や音質の良さなど総合的に見てラヴェル入門の推奨盤として挙げたいです。Evidence Classicsは自身が優れた演奏家でAparté、Ambroisieなどに関わってきたNicolas Bartholoméeが発足したレーベルなので、演奏家の質も音質に関しても目が肥えていて、どのアルバムも一級品です。最近よく見るような高級録音機材を揃えただけの三流新興レーベルとは格が違います。
DGGが激推ししているDaniil Trifonovからは意外なアルバムが出ました。「BACH: The Art of Life」というタイトルなのですが、これがかなり良いです。
トリフォノフといえばラフマニノフやリストの超絶技巧速弾きみたいなイメージがあるため、今回もタイトルのバッハってもどうせブゾーニとかだろとスルーしていたのですが、トリフォノフ嫌いの友人から「意外と良いぞ」と言われて聴いてみたところ、私も考えを改めました。
J.C.・W.F.・C.P.E.・J.C.F.とバッハ一家を遡り、「アンナマグダレーナのための音楽帳」から、メインの「フーガの技法」というカッコいい選曲です。リストとかをあれだけ弾けるトリフォノフなのでコントロールが絶妙に上手く、弱音はまるでハルモニウムのように丸く粒立ちの良い響きが味わえます。よくバッハはチェンバロじゃないとなんて言う人もいますが、そういうアルバムはすでに沢山あるので、たまにはこんなのも良いのではと思います。最終フーガはトリフォノフによる補完で、結構主張が強いですが、アルバムの終わりを暗示しているようで悪くないです。締めにマイラヘスによる「主よ、人の望みの喜びよ」のアレンジで終わるというのも高揚感があって気持ちのいいアルバムです。
Harmonia MundiからはVadym Kholodenkoのリリースを毎年楽しみにしており、2021年はチャイコフスキーの大ソナタでした。大ソナタというと無駄に長いというイメージがあって、あまり好んで聴くこともなく、どちらかというと四季とかの小品の方が好きだったのですが、今作はKholodenkoのスピーディーで明快な演奏のおかげで飽きずに聴き通せました。
彼のこれまでのプロコフィエフアルバムと同じノリで、あえて全開は控えて明晰な解釈に徹しているため、ハーモニーが重くなりすぎず聴き疲れしません。ところで、ファツィオリホールでBrad Michelの録音という、これまでのアルバムと同じ組み合わせなのに、なぜか今作だけDSDやDXDで出なかったのが残念です。(後日出るかもしれませんが)。
マイナーなピアノ作品で意外と良かったのが、Grand PianoレーベルからCharlene Farrugiaのハチャトゥリアン集でした。「7つのレチタティーヴォとフーガ」「子供のアルバム」という二作を収録しています。
ハチャトゥリアンというとソヴィエト作曲家としてショスタコーヴィチやプロコフィエフなどと比べればマイナーな存在で、剣の舞、スパルタクス、仮面舞踏会といった豪奢な演目しか知られていないかもしれませんが、今作のような小曲も捨て置けません。特に「レチタティーヴォとフーガ」は一見学術的で淡々とした作風のようでいて、ハチャトゥリアンならではの民俗的な親しみやすさも持っており、なんとも不思議な作品だなと思ったら、若かりし頃の習作を晩年に手直しした作品だそうです。「子供のアルバム」も同様に、一巻は1947年、二巻は1965年に、それまで書いてきた小品から子供向けに適している作品をまとめたということで、多種多様な魅力に溢れています。
Farrugiaの演奏は力強く的確で、フーガの線も崩れずにしっかりと描かれています。「子供のアルバム」はもうちょっと緩く演奏されても良いかもしれませんが、録音自体が少ない作品なので、テキストブック的には最適な仕上がりです。録音はHenry Wood Hallで、音も素朴ながらずいぶん良いなと思ったら、先程絶賛したBISのシューベルト八重奏曲と同じ録音チームでした。
声楽
歌唱関連のアルバムでは、まずSWRからSheva Tehovalの「Prémices」が良かったです。特に優れたオーディオ機器で聴くと絶品の美しい歌声とピアノの掛け合いが楽しめます。
Tehovalはベルギー出身で、生まれはフランス寄り、歌唱の学業はドイツ寄りらしく、今作のプログラムも、フランスからドイツ歌曲に移り、またフランスに戻ってくるという、両サイドを跨った選曲です。
開幕のドビュッシー「忘れられた小唄」から暖かく澄んだ歌声と透明感のあるピアノに感激して、続くリームの「ヘルダーリン歌曲」の無駄が削ぎ落とされたような素の声の魅力から、Rシュトラウスの甘々な「乙女の花」を経て、シェーンベルク最初期のOp.2歌曲集の控えめな美しさ、そして最後にドビュッシーの有名な歌曲といった具合に、構成が絶妙で、わざとらしくならずに歌手の多彩なスキルをしっかり披露できていると思います。どっちつかずではなく、仏独両方の良いところを融合して、しっかり自分の物にできているという印象を受けたので、リサイタルアルバムとしては最良の部類です。
Anja HarterosとValery Gergiev指揮ミュンヘンフィルのワーグナー・ベルク・マーラー歌曲集も何度も繰り返し聴いた一枚です。
Harterosというと個人的にヴェルディの印象が強いですが、そういえばLuisiとのシュトラウスとか、Thielemannとのローエングリンでも良かったなと思いだしました。
今作もまさに彼女の経験豊かな奥深い歌唱にピッタリな選曲で、私にとっては彼女の代表作になりました。「ヴェーゼンドンク」で人間の豊かな感情を歌ってから、ベルクの「7つの初期の歌」で深層心理の奥底に飛び込み、最後にマーラーの「リュッケルト歌曲集」で人知を超えた天上の気分を味あわせてくれます。特にアルバムのちょうど中間になるベルクのTraumgekröntが個人的にターニングポイントのような感じがして一番好きです。
最近このミュンヘンフィルレーベルの音質が非常に良くて、どのアルバムを買っても失敗が無いです。柔らかく何層にも重なりあうようなオケの音響の上で、歌唱がかなりダイレクトに録られているのですが、それでも粗が見つからないくらい完璧でパワフルな歌唱に圧倒されます。パワフルといっても乱暴ではなく、どんなフレーズでも厚みがあって、オケに負けないくらい豊かな質感を持っており、あのゲルギエフとミュンヘンのサウンドが完全にバックグラウンドに徹しているのが面白いです。
Alphaから恒例のSandrine Piauのアルバムはもうフランス歌曲は歌い尽くしてしまったのか、2021年はドイツとイタリアの二方面で攻めています。(古楽器オケがロマン派をやりはじめるのと似てますね)。特に「Clair-Obscur」の方はツェムリンスキー、ベルク(上のHarterosのとかぶります)、そしてシュトラウス四つの最後の歌という事で、とても期待していたのですが、歌唱自体は伝統的なスタイルで概ね良かったものの、いかんせん録音品質が悪くて楽しめませんでした。肝心の歌声の定位が定まらず、ステレオの左右で揺れまくり、声の残響音があるときは左奥から、またある時は右手前からと、不自然に出没するため気持ちが悪いです。オケ楽器用マイクに漏れた声が、ミックス時のバランス調整によって消えたり現れたりするのでしょうか。期待していたアルバムで内容自体は良好だったため残念でした。
一方ヘンデル作品を集めた「Enchantress」の方は得意のバロックオペラということで、しかもオケは一流のLes Paladinsなので、完璧な仕上がりで存分に楽しめました。彼女は数多くのバロックオペラ作品に出演しているので、それらを聴くのと同じような感覚ですが、いかんせんオペラ全曲は長くて聴いてられないという人は、このアルバムが最善のハイライト盤になると思います。これをきっかけにオペラ録音の方にも興味を持ってもらえると嬉しいです。
ヘンデルつながりで、EratoからSabine Devielheの「Bach・Handel」も凄い一枚です。上のPiauとは選曲から歌い方、録音スタイルまでまるで真逆の一枚で、バロック歌唱の懐の深さを教えてくれます。
Piauはタイトルの「Enchantress」というとおり明るく魅了するような役柄を選んで歌ったのに対して、Devielheはバッハのカンタータから始まり、続くヘンデルもブロッケス受難曲やジューリオチェーザレの悲劇的な曲ばかりを集めており、全体的にしっとりした柔らかい雰囲気に覆われています。Devieilheはこれまでのフランス歌曲アルバムでも大好きでしたが、今作も心が洗われるような美しい歌声はいつまででも聴いていられます。
今回はオケもPichonとPygmalionという事で、フランスのバロックオペラの雰囲気にも近いかもしれません。リサイタルアルバムであってもDevieilheらしさ、Eratoらしさをしっかりと出せているため、印象に残る一枚になっています。
男性歌手では、こちらもEratoから、Michael SpyresとMarko Letonja指揮ストラスブール管の「Baritenor」が一番印象に残りました。タイトルどおり、リサイタルアルバムにありがちなバリトンかテノールかという区分けに一石を投じるというコンセプトで、モーツァルトからヴェルディまで様々な役柄のオペラアリアを歌っています(そもそも実際のオペラでもバリトンとテノールの中間にあるようなロールも多いですし)。
私自身、歌手本人にゆかりのある地元の曲を母国語で歌っているようなアルバムが好きで、今作のようにドイツ・フランス・イタリアと臨機応変に言語を切り替えるようなスター歌手はあまり好んで聴かないのですが、Presto、BBC、Gramophone、Diapason、Opera、ICMと主要なメディアが諸手を挙げて絶賛していたので(しかもこの手の作品に厳しい友人にも勧められたので)、せっかくだからと聴いてみたところ、確かに素晴らしいアルバムです。Spyresはアメリカ中部出身で世界中の歌唱をどんどん吸収していったような経歴なので、どの曲を聴いても変なクセも無く、明るく張りがあり、役柄ごとにバリエーションに富んで、大時代的な歌いまわしも躊躇しないようなカッコよさがあります。
オペラ
近頃はライブ公演の収録技術が飛躍的に向上したおかげで、オペラのアルバムリリースが増えてきており、第二の黄金時代を迎えているように思います。
昔みたいに満足いくまでリテイクを重ねた贅沢なスタジオセッションの完成度を超えることは困難だと思いますが、逆に最近の作品はライブならではのリアリズムが高音質で楽しめるという魅力があります。
AlphaからPierre Dumoussaud指揮ボルドー・アキテーヌ国立管弦楽団でドビュッシーのペレアスが出たのが嬉しかったです。このオペラは国際的なオールスターキャストでやっても劇中のフランスの暗鬱な情景が上手く描けないので、なかなか完璧を求めるのが難しい作品です。そういった意味では日本の伝統芸能とかに近いかもしれません。
今作のようにレーベル指揮者オケ歌手陣とフランスで揃えてのリリースは希少です。唯一メリサンドにスイスの若手Chiara Skerathを起用したのもミステリアスで儚い役柄に合っていると思います。演奏スタイルと録音もペレアスの世界観に合っており、決して派手ではないものの、なんだか昔のBaudo盤とかを連想させる素朴な本物感があります。
ちなみに2022年3月にはHMからFrançois-Xavier RothとLes Sièclesのペレアスも出るそうなので、ペレアスファンにとってはなんとも贅沢な話です。
ペレアスといえば、PentatoneからJonathan Nottとスイスロマンドのが出るということで喜んでいたら、いざ聴いてみると管弦楽アレンジだったので、ちょっとがっかりしました。カップリングのシェーンベルクは良いですし、ドビュッシーも演奏は別に悪くないと思いますが、ワーグナーの管弦楽アレンジとかと同じで、肝心のところで歌手が入ってこないと頭が混乱するのと、代わりにフルートとかがメロディをなぞっているのでカラオケや店舗用BGMのような雰囲気があまり好きではありません。
先程オーケストラ作品でも紹介したBISとMälkkiは青ひげもリリースしており、こちらも管弦楽のと同じくらい優れた作品でした。青ひげはフィンランドのMika Kares、ユディットはハンガリーの若手Szilvia Vörösで、どちらもストーリーに合った良い雰囲気を出しています。
冒頭に二分くらいナレーションが入るのがダルいですが、雰囲気作りには良いのでしょう。あいかわらずMälkkiの指揮は硬派でガラスのように透き通っていて、城内の神秘的な空間を見事に描いてくれます。さらに作中で随所にある衝撃的なシーンもオケが鋭利に爆発するので、そのコントラストが凄いです。歌手中心というよりは、二人のダイアログが音楽によって描かれた情景に飲み込まれていくような感覚があり、このオペラの魅力を引き出すのにぴったりの演出だと思いました。
Pentatoneもオペラに精力的で、2021年はJanowski指揮ドレスデンのフィデリオ、Alsop指揮フィラデルフィアのポーギー、Foster指揮グルベンキアンの蝶々夫人と西部の娘など、かなり王道なレパートリーで攻めています。しかもそれぞれMelody MooreやLise Davidsenなど今をときめくトップスターを起用した入念なセッションです。
賛否両論あると思うのですが、私自身はこの手のコンサートフォーマットの作品はそこまで楽しめませんでした。どのアルバムも、演劇というよりはスター歌手のリサイタルアルバムのようなスタイルに仕上がっているため、純粋に歌唱の素晴らしさを楽しみたいならおすすめできると思います。
私はどちらかというと歌声の上手さよりも役にはまったキャスティングの演技力とか、ステージ上のドタバタしたやりとりを楽しみたいタイプなので、コンサートパフォーマンス的に次々とアリアをこなしていくようなPentatoneの作風はどうも肌に合いません。特にポーギーはなぜか「ハイライト」なので、音楽の流れや話の筋が通っておらず、せっかくここまでやるなら全曲通してやってくれよ、と残念な気持ちになりました。
LINNから、Lothar Koenigs指揮ロイヤル・スコティッシュ管弦楽団でシュトラウスの「ナクソス島のアリアドネ」です。
エディンバラ国際音楽フェスティバルの一環での演奏ということで、統一された地味なジャケットなので見過ごした人も多いと思いますが、それにしてもキャストや指揮者くらい書いてくれてもよかったのではと思います。
アリアドネにDorothea Röschmann、執事長にThomas Quasthoff、作曲家には地元スコットランドのCatriona Morisonといった具合に優れた歌手を揃えており、ロイヤルスコティッシュ管もこれまでLINNレーベルで聴いてきた通りシュトラウスの艶やかさをしっかり出せています。
音質がイマイチなのが唯一残念なところで、歌唱は遠く、オケが霧に包まれたように不明瞭で、まるでOrfeoのザルツブルク公演CDを聴いている気分です。内容は悪くないですから、最新録音ではなくで1960年代のラジオ発掘音源だと頭を思い込ませて聴けばそこそこ楽しめます。
それにしても、いつも不思議に思うのは、最近は交響曲などのアルバムのほとんどがライブ公演を元に作成しており、スタジオ録音に匹敵する高音質が実現できているのに、オペラだけは今でもアルバムやレーベルごとにアタリハズレが大きすぎるのが困ります。ステージ上やピットのスタンダードな録り方や、劇場の常設機材が確立していないのでしょうか。
似たような事例で、最近フィレンツェなどのイタリアオペラ公演をDynamicというレーベルが手掛けているのですが、それも同じようにピットオケのサウンドがモコモコで、観客の騒音のほうが耳につくくらいで、ステージ上の歌声も遠くから何枚ものヴェールを通して聴いているような感じです。
せっかく歌唱も演奏も絶品で、歴史的な記録としても意義があるのに、もうちょっと録音技術を向上してもらいたいと常々思っています。これなら同じマッジョフィレンツェでも大昔のガヴァッツェーニとかを聴いたほうが断然良いと思えてしまいます。一方EratoやAlphaなどはオペラのライブ公演から超高音質なアルバムを続出していますから不可能だとは思えませんし、どうにかならないものでしょうか。
優れたライブ公演が優れた音質で収録されている最高の例として、2021年の新譜ではありませんが、以前からずっと欲しかったC Majorの「Tutto Verdi」ボックスセットを思い切って購入したのは個人的に大きなハイライトでした。
ヴェルディ生誕200周年の2013年に向けて、彼ゆかりのパルマ王立劇場が名誉にかけて公演した全26オペラとレクイエムのブルーレイ映像化作品です。2018年に簡易パッケージの廉価版も出ましたが、私が買ったのは初期のデラックス版LPレコードボックスみたいな巨大なやつです。
それぞれブルーレイでバラ売りや音声のみのダウンロード販売もしており、以前いくつか買ってみたところ、歌唱も演奏も映像演出もすべて自分がヴェルディに求めているスタイルにピッタリ合ったので、ぜひいつか全集を買いたいと思っていました。
私の個人的な好みとして、イタリアオペラ録音はまだ劇場付きの歌手というスタイルが残っていた1950年代までが黄金時代で、それ以降に国際化で海外のスター歌手を招致するようになると、劇場の伝統や個性が薄れて凡庸化して、伝統芸能としての本来の魅力が失われてしまったように思います。
その点このブルーレイセットでは歌手陣も地元中心に、まるでCetraみたいなイタリア臭い歌いっぷりが楽しめて、衣装やステージセットなども変な現代解釈などせずに王道に徹しているのが嬉しいです。音質も映像もとても優秀なので、現代におけるヴェルディオペラの「お手本」として末永く語られるべき永久保存版セットだと思います。
先程述べたDynamicのフィレンツェのプッチーニなども本来これと同じくらい永久保存版になるべきなのに、いかんせん音質が悪いのが非常に残念です。
このヴェルディセットの中でも個人的なおすすめはGelmetti指揮の仮面舞踏会です。聴いてみて気に入ったら私みたいにボックスセットを買いたくなってしまうかもしれません。
復刻リマスター盤
往年の名盤に関連して、2021年4月にChristopher Parkerが死去したのが個人的にとても悲しいニュースでした。
1950年代からEMI Abbey Road Studioにてクラシックの黄金時代を代表する録音エンジニアとして活躍した人なので、当時の情景をリアルタイムで経験してきた人がまた一人亡くなったのは残念です。Discogsで彼の作品を観覧すれば、あれもこれも知っている名盤ばかりでしょう。たとえばHMV/Angelのいわゆる金ステ名盤の多くを手掛けており、同世代のPaul Vavasseurとの二人はEMIを象徴するスケールの大きなサウンドを確立しました。
EMIはデッカと比べてCD化の音質があまり良くなかったので敬遠している人も多いかもしれませんが、マスターテープの保存状態は良いみたいなので、最近のSACDやハイレゾPCMリマスターのおかげで本来のサウンドの素晴らしさを取り戻しつつあります。また、当時から一般家庭でも迫力のあるサウンドが楽しめる事を目指したデッカに対して、EMIはかなりエリート志向だったらしく、当時のレコードも近代の最高級オーディオシステムで聴いてみて初めてその真価が図り知れるなんていう話もあるくらいです。なんにせよ、昔は音が細くてシビアに聴こえた作品も、近年のハイレゾPCMやDSD復刻盤を優れたオーディオで鳴らす事で、録音に含まれるホール音響の広大さに驚かされ、逆に同世代のデッカは作為的に聴こえてしまい、これまでの印象が逆転するかもしれません。
指揮者とかが亡くなると追悼ボックスセットが出るのが定番ですが、名プロデューサーやエンジニアの場合はそうならないのが残念です。レーベルの音質の遍歴という意味でも時系列で作品群を聴き直してみるのは有意義だと思います。
Christopher Parkerが手掛けた作品は、ボールトLPOのブラームス、シュワルツコップとフィッシャーディースカウの角笛、デュプレとバルビローリのエルガーなど名盤が多すぎて悩みますが、個人的には、プレヴィンLSOの高音質っぷりは今聴いても圧倒されます。ドイツ至上主義な日本では忘れられがちな作品群ですが、ぜひ聴いてみてください。
名盤のリマスター復刻に関しては、あいかわらずタワーレコードオリジナル企画の圧勝です。2021年も毎月続々と素晴らしいアルバムが高音質で復刻されるので、常になにか予約注文して発売日を待っています。
昨今レコード店が厳しい状況にあるのは理解していますが、もしタワーのオリジナル企画が無くなったら、私の音楽鑑賞の楽しみが半分くらい失われてしまいます。
2021年のタワーSACD復刻はオペラが充実していたのが個人的に嬉しかったです。特にEMI系の作品は従来のCD版の音質があまり良くないアルバムが多いため(Great Recordings of the Century ARTリマスターなど)、タワーレコード版は単純にSACDだからというだけでなく、センスの良いリマスターエンジニアの手腕によって音質が大幅に向上しています。
私自身は2021年はとりわけマタチッチのメリーウィドウに圧倒されました。まるでオリジナルレコードのような鮮烈さと、ノイズの低さ、そしてテープの不具合をあまり気にさせない甘さも兼ね揃えており、まさにレファレンス級の作品に仕上がっています。
一方メータのトゥーランドットはデッカのハイレゾリマスター版で十分満足できているので、このタワー版はそこまで大きく変わったとは思いませんでした。
他にはエテルナやオイロディスクの作品が多かったですが、カイルベルトのマイスタージンガーは昔のCDと比べて重さやザラつきが抑えられてスッキリした聴き味になっています。エテルナはコンヴィチュニーのオランダ人はEterna Collectionで、ケーゲルのパルジファルはBerlin Classicsで、それぞれ既存のリマスターCD版もかなり音が良かったので、今回のSACD化は大幅な改善というよりは新たな解釈といった感じで楽しめました。
エテルナのオペラといえばスイトナーのサロメが大好きなので、今後タワーSACDで出てくれる事を願っています(これもEterna Collection版CDの音がかなり良いです)。
オーケストラ作品もエテルナの復刻が多かったです。エテルナの版権元Berlin Classicsも最近は結構積極的にハイレゾPCMリマスターを出しており、タワーのSACDとほぼ同じタイミングで出たり出なかったりで、一体どういった契約なのかイマイチよくわかりません。
リマスターの成功に関しては一筋縄ではいきません。タワーのSACDでは、当時のレコーディングセッションの音質の良し悪しが鮮明に現れてしまう、という事は言えると思います。
たとえば私はザンデルリンクのシベリウスが大好きで、Brilliant Classicsの廉価版ボックスでは何度も聴いていた愛聴盤なのですが、今回タワーの復刻を聴いてみると、シベリウスとショスタコーヴィチのどちらも硬く粗っぽくてどうにも好きになれませんでした。BrilliantのCDではそれらが上手にぼやけて聴きやすく仕上がっていたのだろうと思います。
逆にマウエルスベルガーのバッハはBerlin ClassicsのCD版と比べても尋常でないくらい高音質になっており、立体的な空間音響と輝くような音色は最新録音でも真似できないような、まさに圧巻のサウンドです。
タワーからは他にもメジャーレーベル音源のSACD復刻が色々出ており、どれも満足な仕上がりでした。オイストラフのベートーヴェンとかはハイレゾPCMもSACDも本家から出ているので、あえて買い足す必要があるかは疑問ですが、ロジェストヴェンスキー「ロシア音楽の饗宴」とかシルヴェストリのドヴォルザークとかは意外と忘れがちな名盤なので、改めて聴き直す機会を与えてくれます。
マゼールのブルックナー5番とロメオはどちらも高音質の決定版として愛聴してきた作品ですし、ベームのベルリンとのエロイカも本家DGGから忘れられがちで肩身の狭い思いをしてきたので、復刻されたのは嬉しいです。ちなみにベームのはベートーヴェン7番とブラームス1番も入ってるのでお買い得です。特にブラームス1番(有名な赤いジャケットのやつ)は本家ユニバーサルSACDとエソテリックSACDも出てるので聴き比べができます。
個人的にはビーチャムの名盤が復刻されたのが嬉しかったです。どちらもLPレコードではオーディオシステムのサウンドを披露するときによく使っていました。数年前のコーガンとかもそうだったように、こちらもTestamentの復刻LPがあまりパッとせずガッカリしたのに対して、今回タワーのSACD復刻はかなり満足がいく仕上がりになっています。シェエラザードとペールギュントというどちらもビーチャムらしいスペクタクル作品なのも良いです。それにしてもタワーは復刻するアルバムのセンスが良いですね。
タワー復刻でも、複数枚セットで高額なやつは購入するか毎回悩んでしまいます。2021年だと、たとえばリヒテルのEMI協奏曲集は名演ばかりで、従来のCD版がショボい音質だったので、購入する価値があると思いましたが、一方でケンペのウィーンフィル管弦楽曲集というやつはワルツや序曲集とかで5枚組13,200円だったので、よほどのケンペファンでないと手が出せないです。
他にも、タワーとALTUSのコラボでCDやSACDの復刻も行っています。こちらはラジオ音源が多いのでアタリハズレが大きいのが難点です。コンドラシンのNHKライブはSACDではなくてもずいぶん楽しめましたが、ギーレンのマーラー3・5・6は4時間SACD6,600円という安さにつられて買ったものの音質がいかにもラジオっぽい粗さで聴きづらいと思いました。
タワーはNimbusのリマスター復刻も始めたのが嬉しいです。SACDではなくCDリリースです。ヘッツェルのバルトークやロジェストヴェンスキーのストラヴィンスキーなど、もともとそこまで音が悪くなかったので、リマスターといってもピンときませんでしたが、ペルルミュテールのラヴェルはずいぶん音が良くなったように思いました。旧CDの風呂場みたいな音響がスッキリして、打鍵が浮き出るような感じです。昔から賛否両論、議論が耐えないアルバムですが、歴史的価値があるので、改めて日の目を見るのは良い事です。これらはイギリスでリマスターされたので文句は言えませんが、できればSACDで出してもらいたかったです。
さらに、廃盤になって久しいバルビローリのシベリウスが再販されたのには驚きました。リマスターの仕上がりがかなり良いと定評があり、中古価格が高騰して一時期10万円近くで売ってました。私の友人もCDショップやネットオークションで中古出品されるのを監視しているくらい欲しがっていたので、今回再販されたのをプレゼントしたら飛び上がるくらい喜んでました。
昨年バルビローリ全集のハイレゾPCMリマスターが本家ワーナーからも出たので、タワーの販売ライセンス関係が緩和されたのでしょうか。本家リマスターも良いですが、タワー版の方が自然な息使いみたいなものが感じられて、私は好みです。
廃盤といえば、2018年発売のモリナーリ=プラデッリのトゥーランドットも手に入りにくく中古価格が高騰しているので、今後ぜひ復刻再販してもらいたいです。
エソテリックは相変わらず復刻するアルバムのセンスが私に合わないようで、一応色々と聴いてみたものの、そこまで印象に残るほどではありませんでした。
忘れ去られた往年の名盤を復刻して世に知らしめるのがタワーの大義名分だとしたら、エソテリックの方はすでに音質で定評のあるアルバムを自己流に手直ししてエソテリックのオーディオ機器デモ用ディスクに仕立てるのが本来の意図でしょう。
2021年はポリーニのショパンとイ・ムジチの四季から始まったので、どちらもクラシックファンというよりは、まさにオーディオマニア向けだという事を象徴しています。それ以降も、カラヤンのアルプス交響曲とトゥーランドット、ポリーニのシューベルトなど、デジタル録音を再度DSDリマスターしているリリースが多かったです。
本家CDと聴き比べてみるとたしかにDSD特有の柔らかい雰囲気みたいなものは出ていますが(というかSACDプレーヤーの特性に依存すると思いますが)、「往年のアナログ名盤がここまで高音質になって蘇った」みたいな驚きと感動が無いので、一枚4,000円も払うのはもったいない気がします。全部でなくてもいいので、たまには意表を突くような作品も出してもらいたいです(2020年はベームのバイロイトのオランダ人やウラッハの五重奏なんかがありました)。
エソテリックはこれまでリマスターを手掛けてきたJVCの杉本氏が2019年に亡くなった事をきっかけに独自のエソテリックマスタリングセンターというのを立ち上げて、新たにJVCから東野氏というマスタリングエンジニアを引き抜いたそうなので、今後の作品がどう変わっていくのか興味がわきます。
屈指の高音質だけれど選曲が渋すぎて誰にも興味を持たれない英国Duttonから、2021年も数枚の面白いSACD復刻が発売されました。プロジェクト存続のためにもぜひ買ってみてください。
ほとんどのタイトルがイギリスの軽音楽みたいなのばかりですが、一般受けしそうなのは主に米CBSソニーやRCAをやっているようで、数年前もブーレーズのバルトーク旧盤とか尋常でない音質に圧倒され、2021年はブーレーズのダフニスと三角帽子、ストコフスキーもマーラー2番とエロイカ、バーンスタインは春の祭典と、派手派手な演目ばかりです。
この頃のCBS・RCAというのは日本ではあまり注目されない時代だったと思いますが、演奏も録音技術も極めて優秀で、別に変なことをやっているわけではないので、高音質SACD化された今だからこそ再考してみるべきだと思います。
メジャーレーベルからは、2020年ワーナーのバルビローリ全集ボックスがハイレゾダウンロードで小出しにされており、ようやく待望のハレとのシベリウス(上でタワーSACDが復刻されたのと同じやつ)と、マーラーが単品発売されました。ジャケットは当時のものを使っていないので、ダウンロードショップで見過ごした人もいるかもしれません。
とくにベルリンとのマーラー9番は歴史的名演なので、最新リマスターでどう仕上がっているか気になっている人も多いでしょう。EMI GROC CDは高音がカットされて詰まったような音になっていて、SACDやHDTT版は若干甘めでゆったりした雰囲気だったのに対して、今回の公式192kHzリマスターはクッキリと鮮烈な、多くの人が求めていたような鳴り方に仕上がっていると思います。シベリウスの方は個人的にはタワーSACD版の方が音色が濃く出ているようで好みです。
ワーナーはバルビローリの次はフルトヴェングラー全集ということで、全60枚ボックスが出ました。最近のこういうボックスは昔みたいな既存CD寄せ集めではなくて全編最新リマスターなのが嬉しいです。フルトヴェングラーマニアなら買っていると思いますが、私は60枚を全部聴く自信が無いので、とりあえずリマスターの効果が期待できそうなフィデリオや神々の黄昏などをかいつまんでダウンロード版を買いました。バルビローリ同様、旧盤と比べると過度なノイズ除去などもせず概ね好印象です。
フルトヴェングラーといえば、1953年ローマの指輪も最新リマスターで登場しました。カッコいいジャケットなのでどこのレーベルかと思ったらAndromedaだったので驚きました。Andromedaといえば遺影みたいな白黒ジャケットで初心者は絶対に敬遠するレーベルの代名詞だったのに、こんな派手なジャケットだとは想定外です。
一つ不思議なのは、Prestoとかを見ると、ラインとワルキューレだけ48kHz/24bitで、残り二つは44.1kHz/16bitなので、揃えるにしても中途半端で気持ち悪いです。
なんにせよ、1950年スカラ座の方はキングレコードのDSD版がありますし、昔みたいに怪しいCD-Rレーベルとかに手を出さずにダウンロード購入できるのは良い時代になりました。
レーベル公認のリマスターCDを黙々とリリースしているEloquenceからも、クーベリックのマーキュリー作品やマーク、コリンズ、リッチなど、なかなか玄人好みなリリースが続きました。
とくにデッカモノラル世代は古いCDボックスが廃番で高価だったり、バラ売りで揃えるのが大変だったり、コリンズのシベリウスとかは作曲者存命時に近い全集として改めて聴いてみる価値がありますし、マークも忘れがちですが、そういえば名演だよね、という作品が多いので(メンデルスゾーン3番とかパイネマンのドヴォルザークとか)Eloquenceの存在はありがたいです。リマスターは相変わらず優秀ですが、いいかげんハイレゾPCMで売ってくれませんかね。
それと、Eloquenceは相変わらずリリースごとに出しているYoutubeプロモ動画が渋すぎて笑ってしまいます。まるで地方テレビ局の通販番組で売ってる名曲コレクションみたいなノリで地道に頑張っているので、つい応援したくなってしまいます。
ダウンロードショップを巡回していると、たまに単発で変なアルバムがハイレゾリマスターでリリースされているのに遭遇するのが不思議です。このドラティのチャイコフスキー交響詩集も存在すら忘れていたのに、ハイレゾニューリリースで出ていたので改めて聴いてみると悪くなかったりします。こういうのは一体どういった経緯で復刻されることになったのか気になります。
Berlin Classicsによるエテルナのハイレゾリマスターもショップごとにあったり無かったりで全貌が掴めないのですが、このスイトナーのモーツァルト序曲集はとんでもない高音質で愕然としました。しかも東独で高音質といえばのSKDではなく、SKBとの録音です。こういうのを聴くと当時の録音技術の高さに脱帽してしまい、2021年でも全く進化してないな、むしろ多くの新譜を聴く限り、音質に関しては逆行してるかも、と思えてしまいます。
もう一つ、これはハイレゾリマスターでもなく、いつリリースされたのかも不明なのですが、どこかのショップを観覧していて偶然見つけた、SupraphonのHurnikのドビュッシー前奏曲集には感動しました。演奏の解釈も録音スタイルも自分にとって理想に近いです。
Supraphon自身もあまり積極的に復刻しているアーティストではないみたいですし(2012年にドビュッシーがもう一枚復刻されているくらいです)、こういう作品がまだまだ眠っていると思うとワクワクしてきます。タワーもノイマンとか交響曲集だけでなく、こういう小品もSACDで出してほしいです。(売れ行きは期待できそうにありませんが)。
おわりに
私のJRiverプレーヤーを確認してみたところ、2021年に購入したクラシックの新譜は大体200枚くらいでした。旧盤や復刻盤も含めるともっと多いです。
そんなに沢山の新譜をチェックしても、一度しか聴かないなら無駄じゃないか?往年の名盤を繰り返し聴くほうがいいのでは?と言われるかもしれません。
たしかに、新譜の中でも愛聴盤になって10回以上聴いたアルバムは少数派で、相性が悪くて一度しか聴かなかったアルバムもあります。
近頃の私にとって、新譜を買うのはコンサートに行くような感覚になっており、一度きりしか聴かなくても無駄とは思わなくなりました。とくにコロナで海外のコンサートに行けなくなったので、コンサートチケットを買う感覚で新譜を聴けば、当たり外れがあって当然で、若手のイキった演奏を聴くのも、音質がイマイチなのも、そこそこ楽しめます。
そうは言っても、2021年の新譜をざっと眺めてみると、Alpha、BIS、HMなどメジャーなレーベルが多く、マイナーレーベルはあまり購入しなかった事に気がつきました。私も数年前までは演目重視で結構手当り次第に買っていたのですが、特にダウンロードになってからは演奏や録音がかなり酷いアルバムに遭遇する事が増えてきたので、徐々に慎重になっていきました。
レーベルやプロダクションの情報すら無いような、自費制作アルバムみたいなのも多くなり、そういうのはいつもギャンブルです。友人とプレビューを聴きあって「これどうだろ?聴いてみるべき?」「チェロの音程がダメだね」なんて事前に確認しあってリスク回避するのが毎週の習慣になっています。
なんにせよ、これだけ多くの新譜が出ているというのは良い事ですし、それだけレコーディングに対するハードルが低くなったおかげで、新人アーティストの自己プロデュースにも有利な時代になったとは思います。
しかし、アルバム販売というフォーマットは先が見えていますし、ストリーミングでの再生回数も見込めず、コロナで演奏会のチケット売り上げや物販手売りも大打撃を受けたわけで、これから新人アーティストがどのようにして世界に打って出るのかというのは大きな課題だと思います。
たとえば現在一番収益化が見込めるYoutubeにおいても、他のコンテンツと比べてクラシック関連動画はまだまだ開拓するポテンシャルを秘めています。ポピュラーなクラシック系動画を見ると、伝記で読んだような作曲家の一生や、面白エピソード、クラシック業界のクリシェなど、音楽の内容そのものとは無関係のネタで「音楽を聴かずに、周辺の知識だけを得る」コンテンツが多いのが残念です。
Youtubeでは音楽コンテンツ自体が鬼門で、見知らぬ第三者から著作権侵害報告されて収益化剥奪される事例がよくあり、そのあたりのネット上の著作権ルールが健全化するまでは、本格的に参入するリスクが大きすぎるという問題もあります。
数年前に、自身がバッハを演奏した動画をアップした人が、某大手レーベルに著作権侵害で差止めされた、なんて間抜けな話がありましたが、2021年になっても、音楽教師が月光ソナタの弾き方動画をYoutubeに上げたらレーベルから著作権侵害で差し止めになり、抗議してもYoutubeは無視を続け、結局Reddit経由で炎上してようやくYoutubeが動いた、なんて事もありました。
なぜこんな事が起こるのかというと、楽曲はパブリックドメインでも、演奏録音は著作権があるため、もし自身がアップロードした演奏がとある有名ピアニストの録音と似ている部分があったなら、YoutubeのAIがそれを著作権侵害と認識してしまうという事です。
なんにせよ、こういうAIのバグは、通常なら異議申し立てで解消するはずなのですが、著作権ゴロと呼ばれる悪徳レーベルもあり、もしそれらに引っかかると、異議を受けても侵害だと主張しつづけ、渋々レーベルの主張に同意すると、その演奏動画で得た広告収入が全てレーベルの手に渡ってしまい、もしそれを拒絶すれば著作権侵害で訴えられて、繰り返せばYoutubeチャンネルも閉鎖されてしまうという、つまり弁護士を雇う金も暇も無い一個人としては、泣き寝入りするしか無いという問題です。これに関して過去の事例を見ると、Youtubeはそれこそ炎上してニュースにならない限りアーティスト側に手を差し伸べることは稀なようです。
本来そういったトラブルから守ってくれるのがレーベルの役割だったわけで、その保護下に入らず独自の道を進もうという新しいアーティストにとって、昔のレコードやCDに代わって、安心して自身の演奏を世間に聴いてもらえるプラットフォームが整備されておらず、音楽以外に考える事が多すぎるのが、現在の大きな問題だと思います。
結局、今のところ音楽に限らず芸術全般でネット動画界隈で成功している人の多くはライブ投げ銭やメンバーシップ、Patreonなどで裕福なファンに現金でお布施してもらい、ある程度貯金できたら自身でライブツアーを企画する、というようなスタイルに落ち着いてきており、そうなると、まるで貴族のパトロンとして生計を立てていたモーツァルトの時代に逆戻りしたようで、面白い現象だと思います。
そんな古い曲をなんでわざわざ何度も演奏しているのか、今更クラシックを演奏するのは無意味ではないか、という主張も根強いのですが、やはり人間の欲求として「演奏したいと思えるほど優れた楽曲」だから、仕方がありません。こればかりは楽器演奏の経験が無い人には理解できない事だと思います。
2022年になっても、クラシック音楽の魅力が損なわれたわけではないので、きっと将来的には演奏が多くの人に聴いてもらえる新たな道が切り開かれると思いますが、それがどういったフォーマットになるのかは私も想像すらできません。
それまでは毎週コツコツとダウンロードショップで新譜をチェックして聴いてみる事にします。